刀に魂を宿し、そして魂には刀が宿った刀鍛冶(かたなかじ)
 tells-market®︎
tells-market®︎Related Products
関連品物
FAIRBEANS | フェアビーンズ サddスティナブルスペシャルティーコーヒー・チョコレート

¥1,200
tells-market®︎
フェアビーンズコーヒーは、オーガニック・フェアトレード・シェイドグロウン(日陰栽培)の持続可能なコンセプトに基づいた、生産者と自然環境に負荷をかけることなく生み出された「サステイナブルスペシャルティコーヒー」です。

¥5,000
tells-market®︎
自社で製造されるフェアビーンズコーヒーを通して、フェアトレードを身近な選択肢の1つにできるよう幅広く展開してきたFAIRBEANS
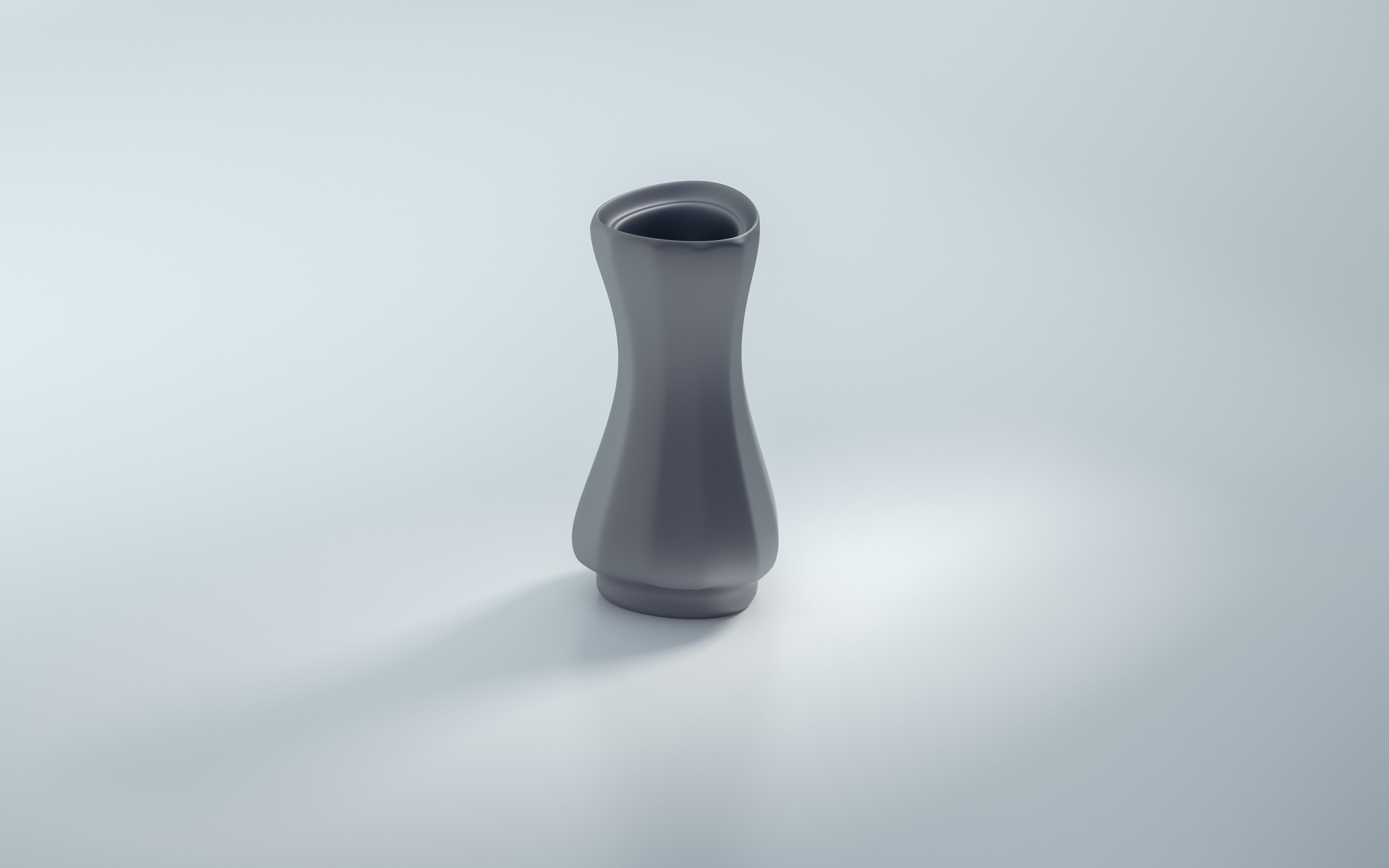
¥15,000
tells-market®︎
ペルーから届く良質なチョコレートとココア

¥1,400
tells-market®︎
[定期購入] お野菜セット

¥800
tells-market®︎
森から得られたバナナやオレンジなどの果物、アボガドやプラタナス、豆類などの食料を提供することや、市場で販売して副収入を得ることによって、家計を支えることにも繋がります

¥1,000
tells-market®︎
フェアトレードは、途上国における多くの農業従事者が経済的自立を達成するための大きな手段の一つであると同時に、現在私たちの見えないところで、急速に進んでいる森林破壊や環境汚染を食い止める防波堤の一つとなっています

¥12,000
tells-market®︎
ペルー国内でチョコレートの加工まで行い輸入

¥12,400
tells-market®︎
2009年に新設されたJICA中部センター・なごや地球ひろば1階買物ゾーンに直営店を運営
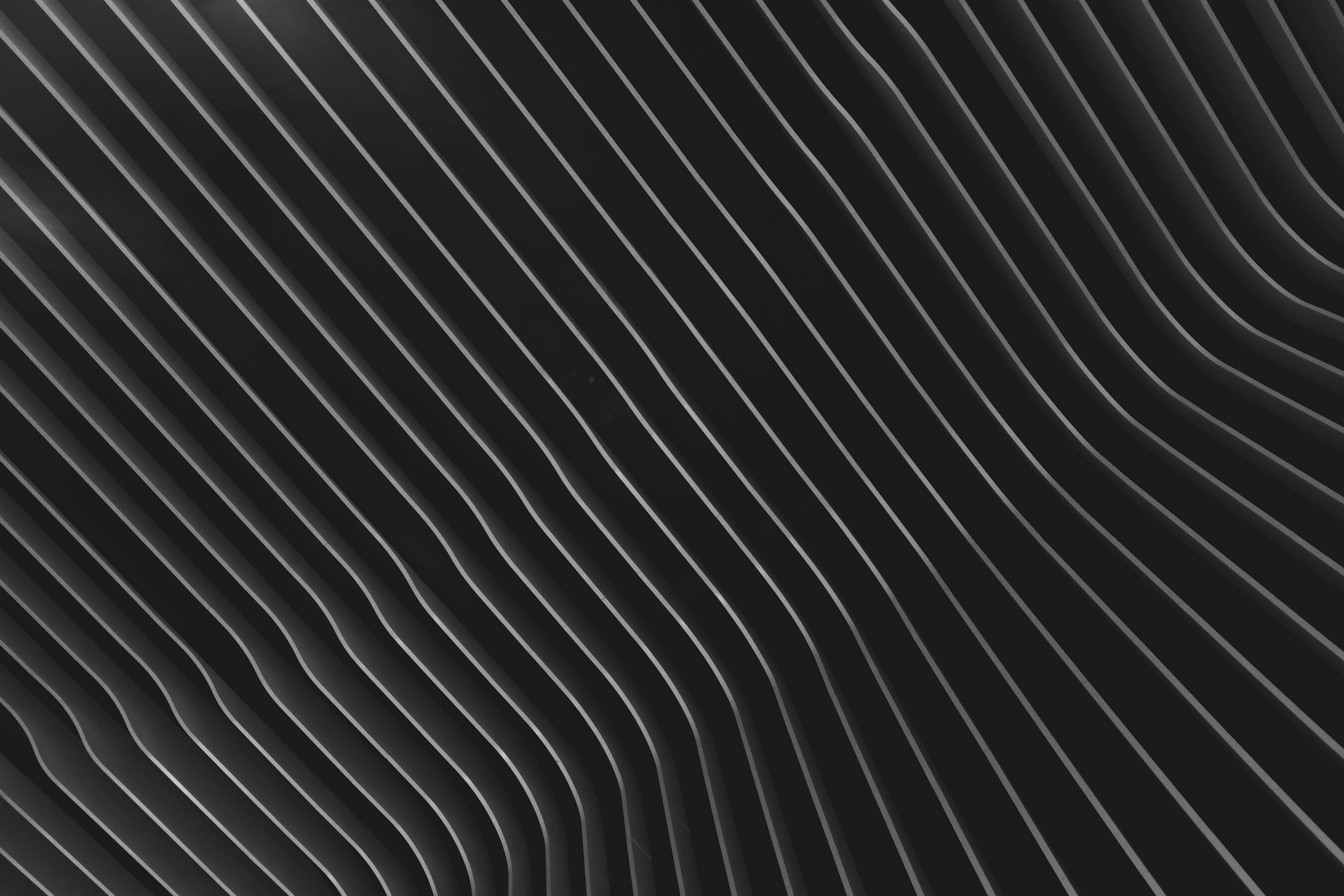
¥1,000
tells-market®︎
多くの生産者の声を聴き、フェアトレードコーヒーが生産者へ適正な額が確実に渡り、生活が改善されていることを実感しました
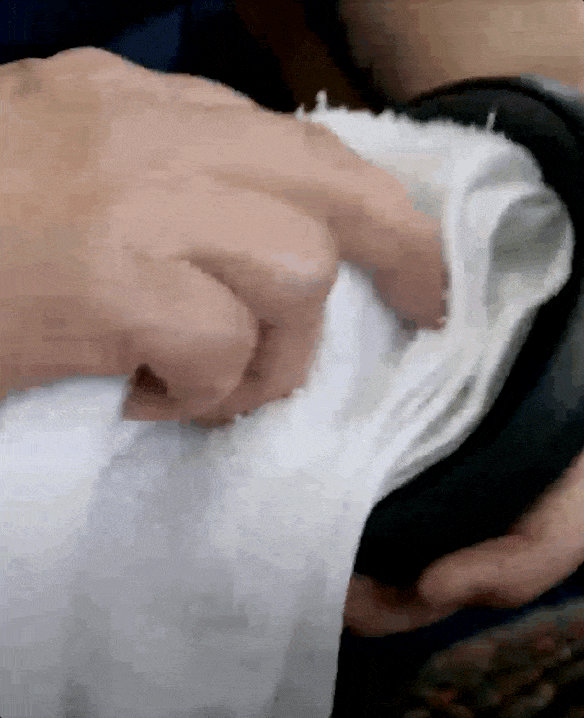
¥1
tells-market®︎
中米での経験や学びを活かし、消費活動の現状を変えるために何が必要であるのか、そのために何をしなければいけないかを考え、より多くの消費者の手にオルタナティブな選択肢を提供していくことを決意

¥14,000
tells-market®︎
植物や多くの木々は、病気や害虫が広がるのを自然のバリアーのように防いでくれます。

¥50
tells-market®︎
景観重要建造物である「文化のみち橦木館」にてカフェ運営、名古屋市内に直営店舗運営を経験し、フェアトレードを発信する場も行ってきました。フェアトレードの理念を共有できる場所、フェアトレード活動全般に関わりたい人たちと接点を持ちながら、多くの市民、消費者に情報を発信し、フェアトレードという選択肢を提供することができること考え運営がされてきました。

¥12,000
tells-market®︎
Is Eco-Fashion the True Future of Style? Let's Dive Deeper into Ethical Threads and Choices

¥2
tells-market®︎
Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥2
tells-market®︎
Astonishing role Culture and Craftsmanship play in Unlocking the Beauty of Earth's Future

¥2
tells-market®︎
The idiocy of designing limitless economic growth when the planet is running out of resources

¥3
tells-market®︎
Are Local Coins, WEB 3.0, and NFTs enough for Forging a Digital Economic Utopia in Japan?

¥2
tells-market®︎
Can we use Blockchain for Social Impact?

¥7
tells-market®︎
刀に魂を宿し、そして魂には刀が宿った刀鍛冶(かたなかじ)

¥1,000
tells-market®︎
『何者かになりたい』 その想いが見つけたカンボジアへの愛

¥1,000
tells-market®︎
大事なことは人を愛すること

¥1,000
tells-market®︎
自分が作っているもので地球を汚したくない

¥1,000
tells-market®︎
無理して笑わなくても大丈夫

¥1,000
tells-market®︎
身体の循環、社会の循環、そして人生の循環

¥1,000
tells-market®︎
本当にいいタオルには終わりがない

¥1,000
tells-market®︎
舌を磨くのは私たちの健康のために そして私たちの地球を磨くために

¥1,000
tells-market®︎
この世界は、人間だけのものではない

¥1,000
tells-market®︎
野菜は文化財である

¥1,000
tells-market®︎
Is Eco-Fashion the True Future of Style?

¥10,000
tells-market®︎
Is the shift from consumer to prosumer the ultimate step to sustainability?

¥10,000
tells-market®︎
Score Testing Product

¥1,400
tells-market®︎
日本では古来から「モノを大切にすること」を美徳としてきた。長年使った物には自分の魂が宿ると考えられ、モノに対しても人に対する時と同じように愛情を持って接して、魂を吹き込んだ。
そんな魂の吹き込まれたモノは家宝として、代々受け継がれ家を守っていった。
刀鍛冶として刀を作る仕事をしている日本玄承社の黒本さん。
物心ついた時には刀の美しさに心を奪われ刀に惹かれていた。そして、厳しい刀鍛冶の修行を経て、刀鍛冶職人になった。
「注文してくれた方々の魂を刀に込め、その家族の特別な物になることが喜び」だと言う。なぜ刀を作るようになったのか?そして現代においての刀の意味とは?日本玄承社の黒本さんの想いとストーリーを聞いた。
・
「刀を好きな理由を言葉で説明はできる物ではないんです」
幼少から刀の美しさに魅力を感じていた黒本さん。アニメ、時代劇、映画などで刀が映っているシーンに見惚れてしまっていたそう。
刀の何が好きなのか?と聞いても、本人も明確な言葉で刀が好きな理由を説明できるものではないそうで、純粋に刀の存在に惹かれていたそうだ。感情が自然と動くことに理由はつけられないもの。
黒本さん自身に刀の魂が宿っていたと言っても過言ではないかもしれない。

刀に惹かれていた黒本さんも20代に入り、いよいよ人生をどのように生きていこうか決心しないといけない年になった。しかし、その時も迷うこともなく刀鍛冶職人になる選択肢が浮かんできた。
刀鍛冶職人になるには険しき道のりになることを承知ではあるが、そこに特段の覚悟や、決心したという思いはないそう。幼き時からの「刀への憧れ」は「刀鍛冶職人として生きる」と言う道へ、さも当然であるかのように導いてくれた。

24歳で刀鍛冶になるべく、東京の吉原義人(よしはらよしんど)刀匠(とうしょう)に弟子入りを頼み込む。この吉原義人刀匠は20代の頃から天才刀匠と讃えられ、東京都指定無形文化財保持者に認定される刀匠なのだ。
だが、最初は弟子入りを断られる。刀鍛冶の多くは責任の重さから弟子を取ることに消極的な人がほとんどであり、よほど運が良いか、もしくは紹介者がいないと、なかなか弟子入りできないのが実情なのだ。
しかし黒本さんは自分の刀への想いを伝えるべく、大阪の自宅から東京に引っ越しまでして、何度も何度も刀への想いを吉原刀匠に伝え、ついに刀鍛冶の弟子として認められる。

修行の身であるので、給料などは発生しない。月曜日から金曜日まで朝8時から夕方6時までは師匠の元で刀鍛冶について学び、平日の夜の時間帯と土日はアルバイトをして生活するための食い扶持を稼ぐ。そんな体力的にも過酷な期間が5年も続いた。
刀鍛冶を志しても、金銭的に生活に耐えきれず辞めてしまう人もいれば、刀鍛冶としての技量がないと判断されて師匠から破門を言い渡される人もいると言う。しかし黒本さんはそんな過酷な修行時代でも刀鍛冶を辞めることは一度も考えなかった。黒本さんの魂に宿っている刀が錆び付くことはない。

刀鍛冶になるには5年間の修業を終了後に文化庁が主催する「美術刀剣刀匠技術保存研修会」に参加し作刀の試験を受ける必要がある。
黒本さんはその試験に一発で合格することができた。その試験も誰しもが合格できるわけではない。吉原義人刀匠と言う優秀な刀鍛冶の元で自分の腕を磨くことができたから、合格できただろうと黒本さんも師匠への感謝を述べていた。
晴れて合格を果たし刀鍛冶職人の道の第一歩を歩むことになった。
吉原義人刀匠と同門の山副さんと宮城さんの3人でとと一緒に京都に工房を建てて刀鍛冶としての人生がスタートした。そのとき黒本さんは36歳であった。
・
「刀とはなんだろうか?」
辞書で「刀」と言う単語を調べてみるとこのように書かれている。
1 武器として使った片刃の刃物。
2 江戸時代、武士が脇差(わきざし)とともに差した大刀。
3 太刀の小さいもの。
4 小さい刃物。きれもの。
刀は武器としての使い方が主流だ。黒本さんも刀鍛冶職人として刀を作成する時にはいかに折れない、曲がらないなどの切れ味がいいものを作れているかという要素には最大限に拘っている。
しかし刀と向き合っていくうちに刀は武器として追及された機能美だけでなく、精神性の高いものでもある事に気づいていく。
刀は各時代で、権力者の証、武士の魂、お守り、宝物など、その所持する人の「精神的な寄り所」としての役割を担っていた。

合戦で刀を持っている武将の姿はイメージできるだろう。しかし現実の合戦で相手を討ち取るために使われた主流な武器は弓矢なのだ。刀はあまり使われることがなかった。
ではなぜ武将たちは刀を持ち歩き戦に挑んでいたのか?それは刀に魂を吹き込むようにして、戦の勝利を信じ無事を祈るため、一種の御守りのような役割が近かったのだ。
これは「現代にも通じる」日本刀を所持する意味になると黒本さんは言う。
これから人生において大きなチャレンジをする時。成功するという魂を刀に込めて飾る。
自分の生きていた証や信念を刀に込めて、子ども、そして孫の世代まで刀を引き継がせる。
現代のモノが溢れる時代において、モノが劣化することなく、100年200年も残るものがあるだろうか?この日本刀の原料に使われている「玉鋼」は世界で一番純粋な鋼と言われる。刀だけは永遠にこの地球に残り続けてくれるのだ。
そんな刀に自分の想い…自分の魂を吹き込む。
刀は人と共に寄り添い、錆びない魂を教えてくれるのだ。

そんな日本文化の代表である「日本刀」だが、現代の生活において身近な存在ではないのが実情である。もっと刀の魅力を多くの人に知ってほしい、そんな思いから製作したのが
「エントランスナイフ『初』Hajime」である。
日本刀と同じ「材料・製法」で製作しながら、現代の「日常」でも使用できるナイフである。刀の魅力の入り口になってほしいという黒本さんの想いである。

・
「日本刀の未来・・・」
伝統技術である日本刀。
しかし、その伝統技術も歴史を遡っていくと、騎乗戦が盛んな時代には長めの刀が流行したりなど、時代時代で想いを反映させて刀は違っていたという。他にも刀にはその時代の、地球の自然などを刀の中に入れ込んでいた。
それならば
この現代において相応しい刀はなんであろうか?現代は昔と比べて何が違うのだろうか?現代にしか見えないものを刀に込めて作りたい。他にも音楽を聞いて、その音楽が表現しているものを入れた刀。
現代で出会った人たちの人柄を込めた刀も作れるだろうと黒本さんは刀の可能性を語っていた。

黒本さんは日本刀と言う伝統をそのまま写しているのではない。
写すのではなく、個性と現代を盛り込みながら黒本さんにしか作れない日本刀を探しもとめている。
黒本さんの魂に宿っている刀への想いはこれからも錆び付くことはないであろう。